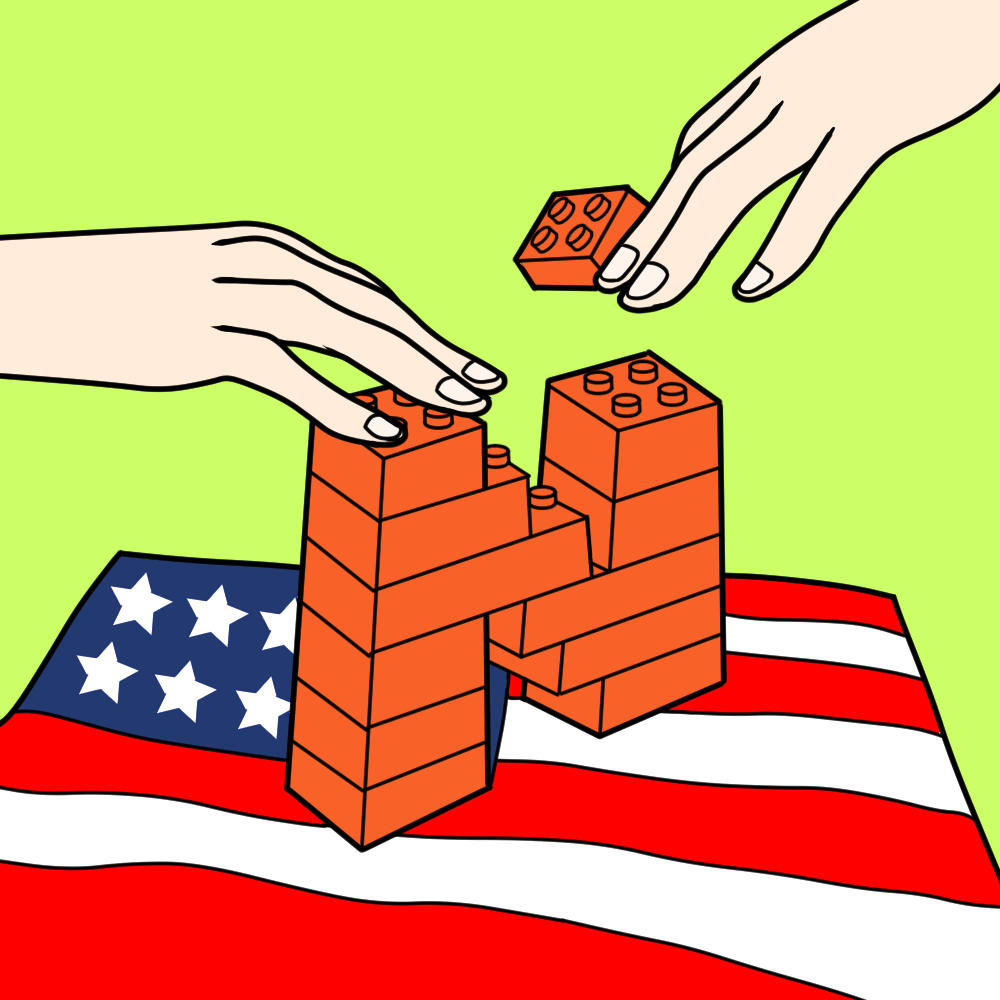 ⒸPiyocchi
ⒸPiyocchi
だってほら、私は特別だから
ところで、みなさんは「バト・ミツバ」という儀式をご存知だろうか。それはユダヤ教徒の女の子にとっての「成人式」のことで、12歳(あるいは13歳)を迎えた女の子は、自分のバト・ミツバ当日、親族や友人や教会関係者の前で、あらかじめ練習を積んできたトーラ(律法)の詠唱を披露しなくてはならない。「ミツバ」というのは「戒律」のことで、ユダヤ教ではこの儀式を経て成人となった子どもたちは、戒律を守ることが(親の監督ではなく)自分自身の責任とされるのだ。
さて、同じ儀式でも「バト・ミツバ」であれば女の子が対象となるが、「バル・ミツバ」であれば男の子の成人式となる。19世紀までは、基本的にいずれのユダヤ人コミュニティでも男の子のためのバル・ミツバのみが執り行われてきたが、アメリカのラビ(ユダヤ教の指導者)であったモルデカイ・カプランは、そうした慣習に否をとなえ、1922年3月18日、世界でも稀だったバト・ミツバを自分の娘のために開催した。以来、ユダヤ教の多くの宗派で、女の子のためのバト・ミツバが祝われるようになったという。(※1)
20世紀のアメリカにて「再発明」されたバト・ミツバ。日本の成人式(あるいは10歳を祝うハーフ成人式)と同じく、女の子たちはその日、儀式の主人公として素敵な自分を演出する。そう言えば、眉毛クイーンのダニも、みずからの生い立ちを語る際にはちゃんとバト・ミツバに言及していた──「ロサンゼルス生まれの私は、都会っ子だった。でも10歳か11歳のときに父親が一念発起して家族でカリフォルニアの田舎に引っ越したの。シティーガール、農場に暮らすって感じね。バト・ミツバには馬に乗って入場したわ。だってほら、私って特別だから。」(※2)
現代アメリカに生きるユダヤ人女性にとって、バト・ミツバとは、伝統に縛られた古臭い儀式というよりむしろ、ユダヤ人コミュニティに生きる個性的な自分といったものが(宗派や家庭環境によって程度の差はあれど)大々的に演出できる、なかなかに貴重なイベントなのだろう。試みにインスタグラムで"bat mizvah"と検索してみれば、ドレスアップした少女とその家族たちの写真はもちろん、激しいビートに乗って踊りまくる若者たちの姿が続々と上がってくる。そう、バト・ミツバの真の醍醐味は、儀式に続いて催されるパーティーの方にあるのだ。
披露宴さながらのバト・ミツバ・パーティーは、そのセッティングをしなくてはならない両親にとっても生半可なことではないのだろう。そもそも、戒律というものに対する責任を引き受ける儀式であるのに、そんなに派手で露出過多なドレスでいいわけ?と目を丸くする親が大多数であることは、私たちにも容易に想像がついてしまう。
今ドキ?ユダヤ式成人式事情
あんなドレスが着たい、あんな演出で入場したい、あんな男の子に見つめられたい......。親の心子知らずとばかり、トーラ詠唱の練習もそこそこに理想のパーティーのことで頭をいっぱいにする女の子、ステイシー・フリードマンを主人公にしたネットフリックスのオリジナル映画『バト・ミツバにはゼッタイ呼ばないから』(2023)は、現代のカジュアルなユダヤ文化を知るのにうってつけの作品だ。
映画は、ステイシーのこんなナレーションで幕を開ける。
世界中で、そしてたぶん太古の時代から、それぞれの文化はそれぞれの方法で子どもたちが大人になる日を祝ってきた。〔ラテン系アメリカ人の〕キンセアニェーラ、〔北米の〕スイート・シックスティーン、それから〔バンジージャンプの原型と言われる、バヌアツ共和国の〕ナゴールっていうのもある。父さんが言うには、ブラジルのアマゾン川流域には弾丸アリの儀式っていうのがあって、腕をヒアリに噛まれるんだけど、その痛みに耐えたら一人前と認められるらしい。でも、それってそんなにたいへんかしらって、私は父さんに言ったわ。ミドルスクールの女子をやる方がキツいはずよってね。
誰にだって通過儀礼はつきもの。それは、私たちだって同じだ。(※3)
ミドルスクールの女子であることの方が、よその国の通過儀礼よりもよっぽど大変なのだと言い張るステイシーにとって、クラスメイトや親族が一堂に会するバト・ミツバのパーティーの成否は、儀式そのものよりもよほどの重要案件なのだろう。ナレーションに続いて画面に映し出されるのは、そんなステイシーが「理想」とするパーティー・シーンなのだが、まさしくそれは披露宴だ。
2005年刊行の原作小説では、以下のように、神に宛てたステイシーからの手紙という形式でこの場面が描かれている。
親愛なる神さま、
昨夜は、これまででサイコーの夢を見ました。そこはバト・ミツバで、私はビーマ(トーラを読み上げる舞台)に立っていて、スピーチを終えた私に、みんながスタンディング・オベーションをしてくれたんです。すると突然、タキシードを着たアンディ・ゴールドファーブ〔ステイシーが憧れている男の子〕が通路を歩いてきて、そしたらなんと、それはバト・ミツバじゃなくて、私のウェディングになっていたんです!(※4)
友だちのバト・ミツバを参考にしつつも、独自のパーティーを構想するステイシーは、物語の前半で、親友のリディアと絶交状態になってしまうのだが、それは憧れの男の子の前で恥をかいてしまったステイシーが、リディアに八つ当たりをしてしまったからに他ならない。恋愛、友情、そして信仰について、とことんこじらせ続けてしまうステイシーの孤軍奮闘は、すべてがコメディーであると分かっているのに、気づくと見ているこちらの胸が苦しくなってしまう。
友情はミツバではない
「いわゆる親の七光りというのには感心しないのだけれど」と、英国紙『ガーディアン』の記者は前置きをしながら、「俳優のアダム・サンドラーと彼の2人の娘が出演しているネットフリックスの10代向け新作コメディ映画『バト・ミツバにはゼッタイ呼ばないから』は、ファミリービジネスの良い部分を見せてくれている」と同作を評価する。「運転ができて皮肉屋の姉ロニーをサンディ・サンドラーが演じ、初めての恋、初めてのBFF〔ベスト・フレンド・フォーエバーの略=親友〕との喧嘩、そして最初で最後のバト・ミツバを迎える妹・ステイシー・フリードマンをサニー・サンドラーが演じる。はっきりいって、どちらの演技もアマチュアだが、サンドラー家の愛情たっぷりな信頼関係と、誰の目にもあきらかな家族の連携プレーは、フィオナ・ローゼンブルーム原作のこの映画を、稀に見るスウィートな作品に仕上げている。」(※5)
そう、本作の見どころは、劇中に描かれるバト・ミツバの現代的なプレゼンテーションのみならず、『パンチドランク・ラブ』(2002)などを代表作に持つアダム・サンドラーという、ハリウッド随一のユダヤ系俳優の本物の家族が醸し出すリアリティの方にもあるのだ。(ちなみに、親友リディアの母親は、サンドラーの妻であるジャッキー・サンドラーが演じている。)
しかも驚くべきことに、ステイシーの「理想」のパーティーは、現実のサンドラー家のそれに比べるとまだまだフツーの部類となるようだ。映画冒頭に展開するクラブのような熱狂空間は、それだけでも十分にありえない感じであったのに、英国紙『ジューイッシュ・クロニクル』の記事によると、2019年に催された長女サンディーのバト・ミツバには、かの〈マルーン5〉のメンバーにして「ユダヤ系ポップスター」たるアダム・レヴィーンがゲスト出演したという。(※6)
そんなサンドラー家が総出で作り上げたコメディー映画『バト・ミツバにはゼッタイ呼ばないから』は、セレブ的な生活に対する観客のあこがれを適度にくすぐりつつも、旧弊な価値観に縛られない伝統的生活の実践といった新世代の「理想」を、なんとかして私たちに届けようとしてくれている。監督のサミー・コーエンは言う、「この映画を作るにあたって私が重視したのは、社会問題だとか家族のあり方だとか、あるいはジェンダーやその他もろもろのことを描くのに、少しでもインクルーシブかつクィアな気分と、ボディ・ポジティブで先進的でZ世代的なものが感じられるようにすることでした。」 (※7)
かくして、映画の中のフリードマン家は、共同体内部に発生する多くの亀裂(それはジェネレーション・ギャップだったり、ジェンダー間の衝突であったり、あるいは収入格差であったりする)を、バト・ミツバという人生の節目をきっかけにして乗り越えていこうとする。
物語が幕を下ろそうとするなかで、ステイシーは神さまに手紙をしたためる。曰く、親友リディアとの仲を修復するために自分が下した決断は──あろうことか、彼女は自分のバト・ミツバを親友のために「犠牲」にしたのだ──、じつは「ミツバ」の精神を実現する善行などではないのです、と。
そう、ステイシーにとっての友情や家族愛といったものは「ミツバ」(戒め、善行)の対象とされるべきものではなく、善きことを為すための前提条件として、みずからの手で護っていくべきものなのだった。監督のコーエンは、本作を「ユニバーサルな体験」としての「親友同士のプラトニックなラブストーリー」であると説明しているが、ステイシーとリディアも、そうした広い意味での「ソウルメイト」なのかもしれない。(※8)
そんなことを考えながら映画を見返してみると、恋もケンカも勉強も、ほとんどすべての出来事を、ステイシーは、「ミツバ」を成していくために欠かすことのできない「準備」として取り組んでいたことが分かってくる。"So Not"というスラングを「ゼッタイ」といった具合に、必ずしも「今ドキ」ではないベタなカタカナ表記で訳してみせた本作ではあるけれど、そこには確かに、「インクルーシブかつクィアな気分と、ボディ・ポジティブで先進的でZ世代的なものが感じられる」新しいユダヤ文化の理想とリアルが描かれていたのである。
───────────────────
本稿に引用されているネットフリックスからの引用は、配信されている日本語・英語字幕を参考にして、引用者が翻訳したものである。
(※1)https://jwa.org/thisweek/mar/18/1922/judith-kaplan
(※2)リアリティ番組『今ドキ!ユダヤ式婚活事情』エピソード1、ネットフリックス、2023.
(※3)映画『バト・ミツバにはゼッタイ呼ばないから』、ネットフリックス、2023.
(※4)Rosenbloom, Fiona. You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah! Little, Brown and Company, 2005, Kindle, Ch.12. 引用者訳.
(※5)https://www.theguardian.com/film/2023/aug/24/youre-so-not-invited-to-my-bat-mitzvah-netflix-movie-review-adam-sandler
(※6)https://www.thejc.com/life/is-adam-sandler-jewish-the-netflix-star-with-proud-hebrew-heritage-tywvvm86
(※7)https://www.cbc.ca/news/entertainment/sammi-cohen-you-are-so-not-invited-to-my-bat-mitzvah-1.6941201
(※8)https://www.thejc.com/life/is-adam-sandler-jewish-the-netflix-star-with-proud-hebrew-heritage-tywvvm86

