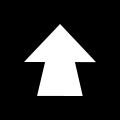岡田秀則+石原香絵対談 無声映画を無音で見るなんて!
書籍『映画という《物体X》』(岡田秀則著)には、映画保存協会の石原香絵氏と岡田氏の対談も収録されています。しかし紙幅の関係で、やむなくカットせざるを得ない部分も多々ありました。そこで立東舎のサイトでは、2016年の「ホームムービーの日」(毎年10月の第3土曜日/2016年は10月15日)を記念して、書籍非掲載部分から対談記事を再構成してみました。
「フィルム、かっこいい」の時代
岡田 石原さんが映画保存活動をされる中で、普段お付き合いをされるのはどういう方々なのですか?
石原 文京区の地域映像アーカイブ事業を請け負って7年目になるので、ご自宅にフィルムをお持ちの方や、同じ街で地域活動をしている方、別の街で似たような事業を始めたいと考えている方からお問い合わせがあったりします。あとは映画館や映画祭の方でしょうか。最近の名画座とかアート系の劇場は地域直結型というのか、いろんなイベントをされていますよね。「ホームムービーの日」も、始めた2003年頃は映画館を会場にすることなどあり得ませんでした。収益につながらないことは、いくらなんでもできない……という感じで。でも、2010年以降は接点が生まれて、これまでに深谷シネマ、松山のシネマルナティック、川越スカラ座、大館の御成座が会場になりました。宝塚映画祭や神戸ドキュメンタリー映画祭の関連イベントにもなっています。
岡田 映画館が自らイベントを組むことがあるし、面白いものであれば持ち込みの企画も認めるようになってきましたね。
石原 そこがすごく大きな変化ですよね。いまは地域の助成金を得ている映画館もあるし、NPO法人になっている映画館もあります。そうすると、「ホームムービーの日」のようなイベントも、受け入れられやすくなりますね。採算とか収益ということが、絶対条件ではないというか……。地元に貢献できることをやりたいという方も増えてきています。
岡田 最近、若い方々が映画館の運営に関わり始めたことが大きいかも知れませんね。
石原 この間も新潟の高田世界館(http://takadasekaikan.com/)に呼んでいただいたのですが、20代の支配人が切り盛りされていました。
岡田 映画作りでは、アメリカではまだかなり重要な監督が「フィルムで撮り続ける」と言っていますけれど、フィルム撮影は日本ではほとんど無くなりました。上映についても、フィルム上映はほぼ名画座とミニシアターのみ、シネコンでフィルム映写機を残しているところは稀です。そんな中、フィルム映写の技術や取り扱いのノウハウを維持したいと思って動いているのはむしろ若い世代ですよね。そういう方が最近増えている気がします。
石原 メディア感覚って世代ごとに違いますから、とても勉強になりますし、刺激にもなります。20歳前後の学生さんは、思いもよらないことをおっしゃいますから。VHSテープを指して「その弁当箱のようなモノ」とか、「フィルム、かっこいい」とか。
岡田 そう、今どきは「フィルム、かっこいい」っていう感覚が生まれていますよね。「大切」ではなく「かっこいい」なんです(笑)。こちらはまず「大切」ということを訴えざるを得ないんですけど、それとは別に、若い人たちは新しい感情を育んでいる。
広がる「ホームムービーの日」
石原 アーカイブズ学では「30年原則」ということがよく言われますけど、時間がある程度流れた時に、価値が見直されて変わってくるものって映画フィルムにもありますよね。「ホームムービーの日」も8mmフィルム普及のピーク(1970年代)からちょうど30年過ぎた頃に始まりました。それでも最初は、抵抗感を示す人がいたんですよ。「なんでそんなものをわざわざ見なきゃいけないの?」って(笑)。それが13年目の2015年には、フィルムセンターが会場になったじゃないですか?
岡田 ホームムービーの日の東京・京橋会場が、ついにフィルムセンターになりました。
石原 参加させていただいてつくづく思ったのは、「ホームムービーの日」には必ずしもあそこまで整った上映環境が必要なわけではないんです。それが、あのイベントの見せ方の難しいところです。
岡田 個人の旧家の畳敷きの部屋で、座布団を敷いて見る楽しさもあるわけですからね。
石原 ホームムービーはやはりお茶の間感覚のメディアですから、古民家やお寺や蕎麦屋さんの座敷などをお借りして、映写機のモーターのカタカタ音とともに上映を楽しんできました。フィルムセンターの会場は小ホールでしたけど、その完璧な映写環境に、どう反応していいのやら……っていう(笑)。でもフィルムセンターが会場になるというのは、きっと昔からの関係者にとって「おお!」っていうことだったと思います。
海外の映画祭でもご活躍の、無声映画伴奏者の柳下(美恵)さんは、「ホームムービーの日」にも興味を持ってくださって、無音のホームムービーに合わせて演奏してくださったりするんです。8mm映写機の最高機種を製造販売していた名古屋のエルモ本社で開催したイベントにもご参加くださいました。そのときに私が「日本ではいくら「ホームムービーの日」が広まっても公的なフィルム・アーカイブの支援は期待できないし、欧米のようにはならない」って愚痴をこぼしたら、柳下さんが「大丈夫よ、そのうちフィルムセンターでもやるわよ」って自信満々におっしゃって。それでみんなで爆笑したんです。「10年続ければそうなるわよ」って柳下さんが余裕の笑みでおっしゃるのを、とても信じられなくて……。でも、本当にそうなりましたね。まさに柳下さんの予言通りでした。
岡田 そもそもホームムービーも劇場の映画と地続きの映画です、ってこと自体なかなか言えなかったでしょう。フィルムセンターもかつてはホームムービーを収蔵対象にしていませんでした。人によって映画のイメージは本当にばらばらで、何を念頭に置いているかは千差万別のはずです。でも、ホームムービーも、映画館で見る映画も、あるいは決まった目的の上映会で映写されるドキュメンタリーも、「あらゆる映画は映画だ」と自然に考えられる寛容さが、保存にかかわる人にはありますよね。この自由さはとても爽やかに感じます。
石原 「内容で選別したくない」という思いはありますよね。でも、そこがなかなか理解されないんですけど。フィルムセンター主幹の岡島(尚志)さんの論考で「KEEP ALLの原則」という言葉を知りました。時々、キープオール! って念じています。
終わった映画のかたちを、どう再生させるか
岡田 無声映画の時代が終わってからは、日本ではどこの上映会でもそのまま無音で上映することが普通で、かつてのフィルムセンターもあまり音楽を付けたりしなかったと聞いています。映画そのものを純粋に味わうという観点では、それも一つの選択です。でも初めて無声映画に出会う人には、じっと見ていて咳払いもできないことに抵抗を感じる人もやっぱりいます。そこで無声映画をどうやって新しい観客に見ていただくかという時に、ヨーロッパでは1970年代後半くらいから、特にピアノを中心とする即興伴奏の文化が生まれています。フィルムセンターも1995年以来、毎年そういう上映企画を催しています。当時の伴奏曲の再現にはこだわらず、現代のミュージシャンの方が即興で伴奏するところが面白い。世界を見渡すと、欧米中心ではありますが、無声映画伴奏専門のピアニストが何人もいますよね。
石原 我々はFPS【註1】というアクロニムを使っているほどですから【註2】、無声映画が適切な「速度」で映写されて、弁士の説明や生演奏付きで上映されることを願っています。柳下さんは「映画館にピアノを!」という運動を継続されていますが、「無声映画を無音で見る」というのは、日本に特徴的なことですよね。どうしてそうなったんでしょう?
岡田 それは映画を純粋なかたちで体験したいというストイシズムじゃないですか? それはそれで意味はあると思います。しかしむしろ今は、伴奏の多様なあり方が興味深いですね。ベルギーの王立シネマテークに行った時に、大ホールと小ホールがあって、小さいホールはなんと無声映画専門でしたが、そのスクリーンの脇に置かれていたのはオルガンでした。そして、時間になるといかにも平常の仕事という感じでオルガニストが出てきて弾く。「ああ、常設のオルガンもいいな」って思いましたね。
石原 ジョージ・イーストマン博物館(ニューヨーク州ロチェスター市の映画・写真博物館)にあるドライデン・シアターも、週に一度無声映画の日があって、専属ピアニストのフィリップ・カーリさんが演奏してくださるんです。でも、それは当たり前のことで、「今日はピアノ演奏付きで無声映画」みたいな構えはなく、終映後は「じゃあ」とお帰りになるという感じでした。
岡田 ぼくは、それが当たり前になっているのが面白いと、日本の目から見て思います。
石原 「日本では、無声映画に必ず伴奏が付くとは限らない」ということは、意外と海外では知られていないんですね。でもそういう違いは、面白いですよね。上映史の違いというか……。
【註1】映画保存協会の英語での名称は Film Preservation Society
【註2】FPSとはFrames per second(=一秒あたりに映されるフィルムのコマ数)、つまり映写速度のこと。トーキー以後は24コマに定着したが、無声映画時代は一定ではなかった
ピアニストと活動写真弁士~無声映画を活かす人々
岡田 イタリアのポルデノーネ無声映画祭でも、入れ代わり立ち代わり世界の主要な無声映画専門ピアニストが出てきます。
石原 職業として成り立っているわけですね。
岡田 ニール・ブランドさんは、俳優もまだやっているのかな? イギリスの方ですが、もともと俳優で、1980年代に無声映画の伴奏ピアニストになった方です。ケン・ローチの『麦の穂をゆらす風』の中で、アイルランドの映画館の観客たちが、条約で決まったアイルランドの独立が不完全だとニュース映画で知って激怒するというシーンがあります。その時の伴奏者がなんとニールさんでした。あの映画はカンヌ映画祭のパルム・ドールを獲りましたから、パルム・ドール映画の伴奏ピアニストというわけです。
石原 弁士の故松田春翠さんが『夢見るように眠りたい』に出演されていますよね。お弟子さんの澤登翠さんが海外公演を積み重ねられて、弁士ですら、いまや海外の方が高く評価されるかもしれません。日本語が分からなくても、音楽のように楽しむのでしょうか。
岡田 あちらではむしろオリジナルの上映形態に近いと見られやすいのですね。日本では、講談とか、話芸の長い伝統の延長に映画説明がありますから、どうしてもレトロ的な捉え方をされてしまうのはある程度仕方ないかも知れません。
石原 澤登さんの影響を受けた若い世代の方もご活躍ですよね。海外に行くと、「若手の弁士さんは国立の学校で養成されているんですか?」って、冗談ではなく普通に聞かれたりします。「まさか、この人達が国の支援を受けずに芸を受け継いでいるなんて信じられない」と。
岡田 ヨーロッパでは、文化やアートを人間存在の本質と考える素地が強いですから、公的支援という発想の位置づけが違うでしょう。
石原 私も昔アテネ・フランセ文化センターで柳下さんの伴奏で無声映画を見ていたときは、企画者に呼ばれてしずしずとピアニストさんが登場するという、あくまで特別ゲストというイメージだったんですね。でも、実は柳下さんは自らそういう場を開拓されてきた、どちらかというとホストなんです。ご自分でイベントを企画されるし、チラシを作って一軒一軒お店を回って配り歩くことも厭わない、無声映画上映の情報を見てそこに伴奏が付いていないと営業に駆けつける。それくらいのガッツで、より良い無声映画上映のチャンスを増やしてくださっているのだと、後になって知りました。
岡田 そして、弁士の方々も大変な努力をされていると思います。しかし無声映画は、「古い映画」じゃなくて「若い映画」なんです。若い映画が今でもそのまま見られるなら、古びるはずがないのです。これからも、カフェでビールを飲むように、日常的に無声映画が観られるような環境を整えたいですね。
NPO法人映画保存協会(FPS)代表。学習院大学大学院人文科学研究科博士課程、単位取得退学。博士(アーカイブズ学)。名古屋学芸大学メディア造形学部非常勤講師。L・ジェフリー・セルズニック映画保存学校卒業後にFPSを立ち上げ、幻の日本映画を発掘・復元・上映する「映画の里親」、国際的な記念日「ホームムービーの日」、東京都文京区の地域型プロジェクト「文京映像史料館」、東日本大震災の直後に立ち上げた「災害対策部」等のボランティア活動を通して映画保存の重要性を訴えてきた。
1968年愛知県生まれ。東京国立近代美術館フィルムセンター主任研究員として、映画のフィルム/関連マテリアルの収集・保存や、上映企画の運営、映画教育などに携わり、2007年からは映画展覧会のキュレーションを担当。また、学術書から一般書まで内外の映画史を踏まえたさまざまな論考、エッセイを発表している。共著に『映画と「大東亜共栄圏」』(森話社、2004年)、『ドキュメンタリー映画は語る』(未來社、2006年)、『甦る相米慎二』(インスクリプト、2011年)、『岩波映画の1億フレーム』(東京大学出版会、2012年)、『クリス・マルケル遊動と闘争のシネアスト』(森話社、2014年)など。