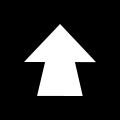芸術作品を通すことで、世界のありようが分かる 飯田高誉インタビュー
書籍『戦争と芸術』では、藤田嗣治、中村研一といった戦時中の戦争画に加え、草間彌生や横尾忠則、細江英公、中西夏之、杉本博司、宮島達男、ヤノベケンジ、太郎千恵蔵、名和晃平、大庭大介、山口晃、Mr.(ミスター)、ダレン・アーモンド、トマス・デマンド、ゲルハルト・リヒター、AES+F、戦闘機グループといった年齢も国籍もさまざまな19作家の38作品を掲載し、戦争との関係を考察している。また、本書籍におけるエッセイのセクションで掲載されている横山大観やフリードリヒ、ターナー、ゴヤ、ヘンリー・ムーア、デュシャン、エルンストなど作品を眺めるだけでは、ただただ美しいと思えるものから、戦争との関係が読み取れないもの、挑発的なものまで多様だが、著者である飯田高誉氏の論考を読み進めると、「戦争と芸術」の一様ではない関係性が明らかになっていく。このような特異な書籍がいかにして生まれたのか、飯田氏にお話を伺った。
われわれの中に戦争を起こす因子がある
——本書では、藤田嗣治で有名な太平洋戦争、第二次世界大戦中の戦争画だけではなく、横尾忠則や草間彌生、そして杉本博司やゲルハルト・リヒターまでと、幅広い作家の作品が掲載されて、戦争との関係が考察されているのが特徴的だと思います。
飯田 国内外を問わず、戦争の記憶を有している作家、また、戦後生まれの作家、さらに戦争の記憶を全く有していない若い作家……この三者三様の世代のあり方や時代状況が、戦争というテーマを通じて浮き彫りになってきます。それから、今われわれがどういう立ち位置にいるのかということ……世界はどうなっているのか。これは、芸術作品を通すことで非常にリアルによく分かってきます。なぜかと言うと、政治的な、あるいは宗教的な立ち位置では自由度が限定されるからです。そもそも戦争というものを突き詰めていくと、人間存在そのものと対峙しなければなりません。つまりは、「自らの中に戦争を起こす因子がある」と思った方が良いのです。他岸のことではなくて、此岸、われわれの中に戦争を起こす因子がある……倫理的善悪、条理と不条理が表裏一体を成しているのが人間であるのだと考えております。それをきちんと見据えていかないといけないし、切り離してしまうと、非常におかしなことになる。例えば、単なる平和主義というものを携えて反戦運動をしても、一向に戦争というものは無くならないわけです。
——無辜の民という視点からでは、状況は改善しない。
飯田 「私達は平和主義者である」、あるいは「反戦主義です」ということを言えば言うほど、自らを棚上げしていることになります。これは危険な論議だと思います。オバマ大統領が広島訪問の際にスピーチした内容はもっともなのですが、政治家としての立場を棚上げして、「空から死が訪れ、世界は変わってしまった」と語ったスピーチ冒頭の言葉が象徴しているように、権力者としての当事者ではなく、私人に近い発言だったのです。オバマ大統領が着任以来、アメリカの核開発に関する予算は増え続けております。この現実を踏まえた上でなければ、このスピーチの効果は半減してしまうのです。
ハンナ・アーレントは「凡庸な悪」という言い方をしていますが、ナチの将校アドルフ・アイヒマンが非常に官僚的で思考停止状態、つまり感情や主観を排して事務手続きによって多くのユダヤ人をアウシュビッツに送り込み、大量虐殺というたいへん悲惨な結果を導いてしまいました。これはアイヒマンの当事者意識の欠如だったのです。「この『業務』を施行しなければ自らのポジションが危うくなり、上から言われたことを事務的に実行したに過ぎない」という主旨のことをエルサレムの裁判所で彼は述べています。
この本『戦争と芸術』では、自ら内在している人間としての自己矛盾を戦争に根差した人間存在の不条理性や神秘性を芸術作品によって浮かび上がらせたかったのです。そのことによって、自ずと欺瞞や偽善も浮かび上がる仕掛けとなっています。では、いま戦争が起こったら、われわれはどのようにメッセージを発信できるのか。今からこのことを想定して、きちんと論議しないといけません。現代の日本の政治的状況を鑑みると危機的状況で、このままだと再び取り返しの付かないことを繰り返すこととなるでしょう。この本をそのような視点で読んでいただければ著者として本望です。
芸術作品を題材にして論議するのが一番良い
——副題になっている「美の恐怖と幻影」という言葉も表裏一体で、とても示唆的ですよね。
飯田 パリのルーブル美術館に行くと、ジェリコーやドラクロワ、ゴヤの古典絵画の名作が展示されていますが、その中には戦争画が含まれています。またテート・ブリテンに行けば、ターナーの膨大なコレクションが展示されています。ターナーも戦争画を描いています。その中でも特に評価されている作品がトラファルガーの海戦でフランス艦隊と交戦した「戦艦テレメール号」を主題にした作品です。その絵の前で佇んでいる観客はそれを美しいと思っている。古典絵画という時間的経過によって戦争の生々しさが薄れ、むしろ芸術作品として客観視されています。実際には、描かれた当時は生々しい戦争画だったはずです。では、なぜわれわれがそういった戦争画に惹かれるのか……。美の陶酔感と恐怖は隣り合わせなわけですが、どうして惹かれるのか……。これを問いただしていくと、やっぱり自らの人間存在そのものに立ち返ってくるわけですね。
——そういったことも含めて、人間というものを考えていかないといけない。
飯田 それを解き明かす1つの方法として、芸術作品を題材にして論議するというのが、一番良いのではないかと考えております。そのような経緯で今回この本を著すこととなったわけです。戦争に関しては、政治的な、あるいは経済的な視点での論議はいろいろされていますが、芸術作品に関しては十分ではないのですね(特に日本では)。ですからきちんと論議を尽くす必要があるし、公共の場で論議ができるようにしていかなくてはいけないのではないか、と考えているのです。
——太平洋戦争、第二次世界大戦中の戦争画は、かなり微妙な立ち位置にあるそうですね。
飯田 戦争画はいったん連合国軍(主に米国)によって接収されて、1970年に返還されたわけですけれど、これはいまだに「永久貸与」という形で、つまりは借りている状態です。それともう1つ、戦争画に対する論議が十分なされてない。ですから、そのまま、終戦から70年以上が経ってしまったわけです。このように戦後の総括がないままでは、いつまでも戦後は終わりません。ですから過去の戦争画についてきちんと検証して、さらに現代の作家たち、戦争の記憶の無い作家たちをも交えて、現代のグローバル化した時代状況の中で行われている戦争というものに接続していかなければならないと考えております。国と国との戦争から局所的な紛争やテロ、時代状況の推移とともに戦争の在り方がドラスティックに変容してきております。これも、この本で訴えたかったことですね。
「戦争と芸術」展を再起動、国内外での開催を準備
——本書は、京都造形大学で飯田さんがキュレーションした展覧会が元になっているとのことですが。
飯田 2007年から2009年にかけて、「戦争と芸術」展を4回にわたって企画しました。この展覧会のインスピレーションの1つとなったのは、ロンドンにあるロイヤル・アカデミー・オブ・アーツで開催された「アポカリプス」という展覧会です。黙示録的復讐と野蛮に満ちた権力構造に憑かれた集団的自我を歴史的な視点によって浮かび上がらせ、また現代社会の闇をも顕在化させたものです。参加作家はジェイク&ディノス・チャップマンや森万里子、ダレン・アーモンド、ジェフ・クーンズらです。黙示録的ビジョンに纏わる超歴史的な終末感や至福千年の意味を、ハイパーリアルな資本主義社会と重ね合わせました。日本と宗教を基軸にした西洋的コンテキストの違いを改めて考えさせられ、また、現代の社会的な状況においても、形を変えた戦争というものが起きているということを実感したわけです。それからもう1つは、義父と一緒に見に行った、かつて海軍兵学校だった場所ですが、今は海上自衛隊幹部候補生を育成する江田島にある第1術科学校所属の教育参考館で、そこで藤田嗣治や中村研一、そして横山大観などの戦争画を見たのです。これは、「戦争と芸術」展を起動させた大きな契機となりました。他にも、ロンドンにあるインペリアル・ウォー・ミュージアム(イギリス帝国戦争博物館と呼ばれているところです)のキュレーターと会い、そこで、アフガニスタン戦争、アウシュビッツ、そして国連の欺瞞的でダブルスタンダードな存在を訴求する映像作品、つまり近現代の戦争をテーマにしている美術館と出会ったのです。そういったことすべてつながって展覧会「戦争と芸術」展を京都で立ち上げたのです。
——さまざまなことが融合して、戦時中・戦後・現代の作家の作品を幅広く展示するというアイデアに結実したわけですね。
飯田 それから三島由紀夫ですね。彼は大正15年/昭和元年に生まれて、昭和45年に自死しています。戦争とのかかわりが深く、激動の昭和を駆け抜けた芸術家でした。実は戦時に彼は徴兵検査で引っかかって、結局戦地へ送り込まれなかったのです。それが大きなトラウマになり、三島由起夫という作家を形成し、表現を行う上でこのことが大きなドライビングフォースにもなったのでした。時代状況に翻弄された運命を自ら体現した作家だったのです。そして、三島由紀夫が自衛隊の東部方面総監室で自決したのが、昭和45年は1970年、大阪万博の年ですね。いわゆる高度経済成長のピークで、イケイケドンドンだった時代です。一方で、70年安保の年でもあります。だから三島由起夫という一人の作家を追っていくと、昭和の歴史が連続したコンテキストとして明確に浮かび上がってくるのです。戦争の記憶を携えた三島が表現してきた小説やエッセイ、演劇、映画「憂国」などは、古びるどころか現代日本に迫ってきております。実は、この本のライトモチーフ(示導動機)は三島由紀夫なのです。
——では最後に、今後の活動の予定を教えてください。
飯田 この本は私にとって今後たいへん大きな存在になるはずです。これをひ1つのきっかけにして、新たな「戦争と芸術」展を再起動させて、第5弾を国内外の美術館で開催する準備を始めました。本書の最後の章で取り上げたゲルハルト・リヒターにもうすこし深く関わり、彼の作品を核にして展開していきたいと考えています。
その一方で、僕は映画も大好きで、特に映画監督デヴィッド・リンチの絵画をフィーチャーした展覧会を3回ほど企画しておりまして、1回目(2001年)にはリンチを呼んで関連イベントとしてトークセッションを行いました。今回の本ではリンチを取り上げておりませんが、彼は戦争、そして暴力を対象化した映画や絵画作品を生み出しています。「人間の心理的な状況を描写すると、それが時として戦争状態に陥っていることがある」という意味のことを語っています。いろんな抑圧的なこと、トラウマ、欲望の構造みたいなもの、これらを作品化している人ですから。ですから今度は、デヴィッド・リンチの展覧会を、「戦争と芸術」という視点でも企画していきたいと考えております。「戦争と芸術」は、私にとってライフワークになりました。(了)

1956年東京生まれ。1980年にフジテレビギャラリーに入社し、草間彌生など現代美術家の展覧会を企画し、1990年に独立、インディペンデント・キュレーターとなる。東京大学総合研究博物館小石川分館アート&サイエンス協議会企画顧問として現代美術シリーズを立ち上げ、「マーク・ダイオン-驚異の部屋」、「森万里子—トランスサークル」、「杉本博司-大ガラスが与えられたとせよ」など連続企画(2003〜2005年)。カルティエ現代美術財団(パリ)にて杉本博司(2004年)と横尾忠則(2006年)の展覧会キュレーション。「スクリーン・メモリーズ:隠蔽記憶」(水戸芸術館、2002年)ではゲスト・キュレーションを委嘱される。第一回「六本木クロッシング」展(森美術館)のキュレーションや第二回「堂島リバービエンナーレ:エコソフィア」展のアーティスティック・ディレクターを務める。また、COMME des GARÇONSの川久保玲の依頼によってアートスペース「Six」のアートディレクターに着任し、森山大道、デヴィッド・リンチ、草間彌生、横尾忠則、宮島達男、中平卓馬などの展覧会を企画。その他に映画作家のデレク・ジャーマン、ピーター・グリーナウェイなどアートワークによる展覧会を企画。京都造形芸術大学国際藝術研究センター所長、慶應義塾大学グローバルセキュリティ講座「政治とアート」の講師などを務め、青森県立美術館美術統括監を経て、現在、インディペンデント・キュレーター 森美術館理事