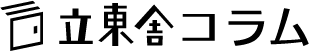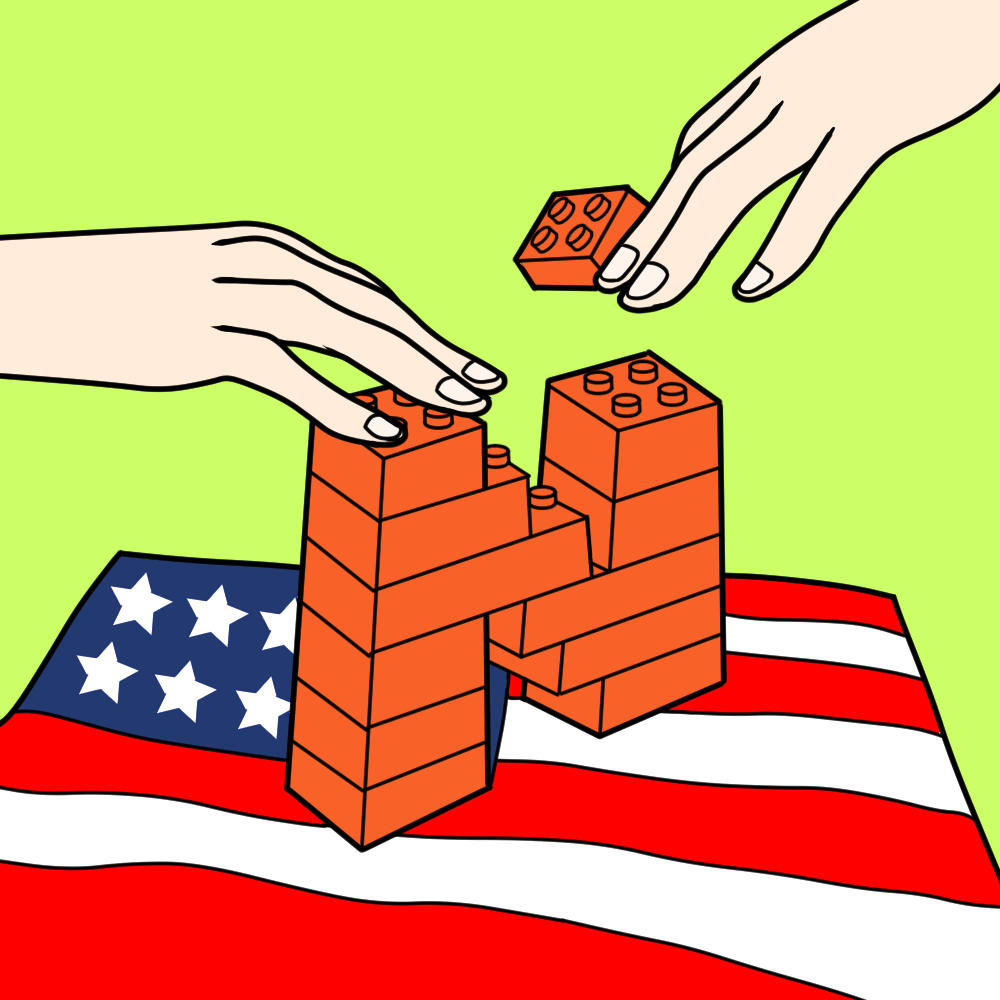 ⒸPiyocchi
ⒸPiyocchi
パレードは終わらない
1960年代の空気を知るかつての青年が半世紀後に2度も大統領に選出され、そして、アメリカとしては34年ぶりとなる大規模な軍事パレードをみずからの誕生日に開催するといった未来が訪れるとは、さすがのモハメド・アリも想像しなかったに違いない。
2025年6月14日に開催された軍事パレードは、その名目こそアメリカ陸軍の創設250周年記念であったが、それはトランプ大統領の誕生日でもあり、かつまた、ヴァンス副大統領の結婚記念日でもあった(とヴァンス本人はスピーチで付け加えた)。
国家権力のあからさまな私物化を見せつけたパレードに対し、全米各地で「王はいらない」(No Kings)と主張する抗議デモが行われたが、ワシントン・ポスト紙も指摘するように、トランプ政権のなしたことは単なる政治的パフォーマンスにとどまらない、ベトナム戦争以後のアメリカ軍の努力を台無しにしかねないものであった。
ワシントンD.C.で最後に開催された軍事パレードは湾岸戦争後の1991年のことで、その目的は帰還兵の歓迎のみならず、ベトナム戦争以後、軍と距離をとってきたアメリカ国民の気持ちを和らげることにあった。〔...〕
今年は陸軍誕生250周年であるばかりか、アメリカ国内においても最も評価の低いベトナム戦争の終戦50周年である。土曜日のパレードは、信頼回復のための何十年にもわたる軍の努力に、致命傷を与えかねなかったのだ。 (※1)
ちなみに、1991年の軍事パレードを企画したのはジョージ・H・W・ブッシュ大統領であったが、彼の息子にして第43代大統領となるジョージ・W・ブッシュもまた、2004年、その軍歴については詐称疑惑が取り沙汰された。ただし、スキャンダルはやがて「誤報」とされ、その真偽は曖昧になったまま、疑惑を報じた報道番組の女性プロデューサー、メアリー・メイプスが職を追われることによって事態は収束している。
ここで興味深いのは、のちにメイプスが出版した自伝をもとに、映画『ニュースの真相』(2015)が制作されたことだ。なにしろ、一度は「誤報」とされた大統領スキャンダルを、その汚名も晴らされていない状態で娯楽作品に仕上げるには、政治的にも興行的にも、いささかリスクが高いと言わざるを得ないからだ。
はたして、メイプスを演じた名優ケイト・ブランシェットの演技は素晴らしく、かつまた、彼女がインタビューで答えているように、同作は「政治的なプロパガンダ」(agitprop)ではなく、もっと根源的な「民主主義とは何か」を問う作品に仕上がったのである。(※2)
ケイト・ブランシェット、ふたたび
すでにネットでも拡散され、メイキング番組『イカゲーム 監督・出演陣が語る』(2025)でも公表されている通り、『イカゲーム』シーズン3(2025)の最後にカメオ出演を果たしたのは、他ならぬケイト・ブランシェットだった。
シーズン1のラストシーンから始まったソン・ギフンの戦いが幕を閉じ、その残務処理をしにイ・ビョンホン演じるゲームのフロントマンが訪れたロサンゼルスの街角で、多額の借金を抱えているのであろうゲーム参加候補者と「めんこ」をするブローカー。韓国の街角では、それはドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』(2016、ネットフリックスで配信中)で人気を博した俳優コン・ユの役どころであったが、それをシーズンの最後にケイト・ブランシェットが引き継ぐとは誰が想像しただろうか?
今後、アメリカ版『イカゲーム』が制作されるか否かはわからないが、やはり物語はアメリカに繋がっていくのだろう──。死屍累々たるゲーム結果のすべてを受け止め、ようやく最終話に辿り着いた視聴者はきっと、こちらを挑発するように見据えるブランシェットの姿を前にして、そうしたこれからの『イカゲーム』の展開を当然のこととして受け止めたに違いない。
アメリカを中心に、現代のあらゆる民主主義国家が直面している問題を、デス・ゲームというあからさまな皮肉によって描き出したがゆえに大ヒットを記録した『イカゲーム』。ただし、同作を単なるグローバルな寓話として観終えてしまうのはもったいない。
というのも、たとえばシーズン2の細部に注目すると、そこには、「アメリカ資本のネトフリが出資した韓国ドラマの語るベトナム戦争」という、一筋縄ではいかない問題が隠されているからだ。
ベトナム戦争に出征したデホの父
アメリカ資本のネトフリが出資した韓国ドラマが語るベトナム戦争とは、いったい何か。世界の視聴者の大多数にはほとんどノーヒントの状態で配信されたのは、シーズン2のエピソード5。
五人六脚で「めんこ」や「コマ回し」や「コンギ(おはじきでお手玉をするような遊び)」に挑戦するという、一見したところ楽しそうだが、生死をかけては決してやりたくないゲームを見事クリアした参加者たちは、つかのま互いの健闘を称えあう。
チョンベ(中年男性) おい、おまえは小さい頃、コンギだけやってたのか? (コンギをする手つきを真似しながら)パパッ、トドッ、チャ! ......って、目にもとまらない手さばきだったぞ。こっちは、武侠映画を見てるみたいだったよ。
デホ(30代男性) 自分は二代独子(父にも自分にも男兄弟がいない男子=大事な後継ぎ)なので、母さんが姉たちと家の中だけで遊ばせてたんです、ははは。
チョンベ 二代独子を海兵隊に入れたのか? そんなに大切な息子なのに?
デホ 男らしくなるようにって、父が入隊させたんです。ベトナムの、ベトナム戦争の参戦軍人だったんですよ、父は。
チョンベ 立派な父さんだな。
デホ ええ。
チョンベ じゃあ、父さんも海兵隊出身なのか?(※3)
この会話で聞き流してはならないポイントは三つある。一つめは、デホはかつて文字通りの「箱入り息子」であったということ。二つめは、けれども彼の父はそんなデホを箱の外に出し、「男らしさ」を獲得させるべく海兵隊に入れたということ。そして三つめは、彼自身も男兄弟のいない「独子」だったはずのデホの父が、遠いアメリカのベトナム戦争に参戦していたということだ。
海兵隊の1140期だというデホは、その入隊時期は2011年のはずであり、対するチョンベは746期とのことなので、1994年の入隊となる。ざっと計算するならば、デホは1980〜90年代生まれで、チョンベは1960〜70年代生まれとなるのだろう。
そんな2人の男性にとって、1940〜1950年代生まれのデホの父はいったいどのような「男」に映っていたのか。『韓国、男子 その困難さの感情史』(2024)の著者チェ・テソプは、現代韓国の男性性というものを考える上で、この世代の重要性を次のように説明している。
1950年代の、国民国家のための男性性を鋳造しようとする試みにもかかわらず、多くの大衆、そして男たちは、国家というものを不信のまなざしで眺めていた。〔...〕国家の先行きが不安なのと同様に、戦争、貧困、徴兵の恐怖に苦しんだ男たちの男性性の先行きも不安なものだった。〔...〕
〔1960年代の軍事政権期、〕新たな男づくりで重点が置かれたのは、韓国の兵営国家化と、その根幹となる強力な徴兵制度の定着だった。(※4)
チェは、1950年から53年まで続いた朝鮮戦争において「男らしさや愛国心が鼓舞されることはなかった」とした上で、この戦争が生み出した「傷痍軍人」たちこそは「国家の暴力、戦争、貧困の犠牲」となった男性性の象徴であると指摘する。(※5)
では、そのような時代に幼少期を送ったであろうデホの父が向かった「ベトナム戦争」とはいったいいかなるものであったか。チェは、かの戦争がもたらした「男らしさ」の幻想を、以下のようにまとめている。
ベトナム戦争は韓国にとって、戦争の廃墟を乗り越えて遠征に赴く立場にまで上りつめた国家、未開のベトナム(の女たち)を(性的に)征服する(帝国の)男、下等で貧しい東洋人ではなくアメリカの勇敢な戦友、という幻想をもたらした。(※6)
もちろん、それはあくまでも幻想でしかなかったが、彼らがイメージした勇敢さは、そのまま部隊の名前にも反映されていた。立命館大学名誉教授の文京洙は、その著書『新・韓国現代史』(2015)にて、ベトナム戦争に派兵された韓国軍部隊の実態を次のように解説している。
青龍、白虎、猛虎などと名づけられた韓国軍部隊は、主としてベトナム中部沿岸地域に駐屯し、全1170回の大隊級以上の大規模作戦と55万6000回の小規模部隊単位の作戦を遂行し、4万1400人の「敵軍」を射殺したとされる。(※7)
このような部隊に配属されたデホの父は、帰国後にさずかった大切な長男に「デホ=大虎」と名付ける。かくして、ベトナム戦争を介して醸成された「男らしさ」の幻想は21世紀の今に引き継がれたわけだが、そんなデホが、シーズン2のクライマックスに勃発した反乱でいかなる活躍をなし得たのか(あるいは、なし得なかったのか)は、ぜひみなさんの目で確認していただきたい。
───────────────────
本稿に引用されているネットフリックスからの引用は、配信されている日本語・英語・韓国語字幕を参考にして、引用者が翻訳したものである。
(※1)https://www.washingtonpost.com/entertainment/2025/06/15/trump-army-parade-washington/ (引用者訳、以下同)
(※2)https://variety.com/2015/film/news/cate-blanchett-truth-interview-1201632118/
(※3)ドラマ『イカゲーム』シーズン2、エピソード5、ネットフリックス、2024.
(※4)チェ・テソプ『韓国、男子 その困難さの感情史』小山内園子・すんみ訳、みすず書房、2024、103-06.
(※5)同上、98-101.
(※6)同上、108. テソプは、この一文の根拠として、韓国外国語大学(グローバルキャンパス)歴史文化研究所が発行する紀要『歴史文化研究』掲載のキム・ミランによる2010年の論文を挙げている。
(※7)文京洙『新・韓国現代史』岩波新書、2015、99.