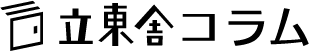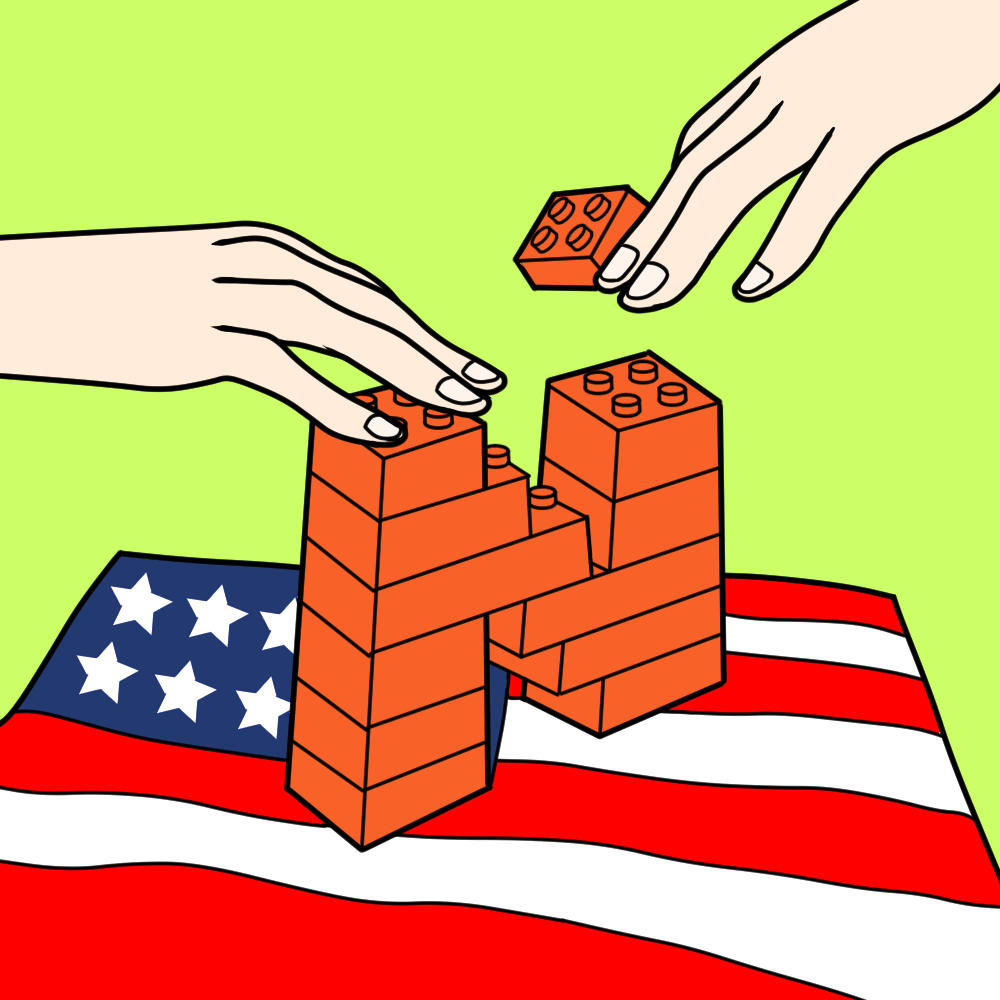 ⒸPiyocchi
ⒸPiyocchi
市販薬は合法ドラッグ?
オーバードーズ。薬物などの「過剰摂取」を意味するこの言葉は、コロナ禍以降、ここ日本でもよく耳にするようになってきた。非合法な薬物はもちろんのこと、一部の処方薬や市販薬には覚醒剤や麻薬と同質の成分が含まれているため、その効果を期待していちどきに大量服用してしまう人があとを立たないのだ。新聞報道の例を見てみよう。
「市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)で2021年5月~22年12月に全国7救急医療機関に救急搬送された急性中毒患者122人は、平均年齢が25.8歳で、女性が97人(79.5%)を占めたことが16日、厚生労働省研究班の調査で分かった」と、2023年8月17日付の記事で報じた日経新聞は、その背景を分析して、「現実逃避などの目的もみられ、若年女性を中心に依存・乱用が広がっている恐れがある」と続ける。
同紙はさらに、2025年2月12日付の記事にて、「警視庁は昨年、薬を無許可で譲り渡した疑いで男らを相次いで逮捕。中高生に定価より安く販売したとされる少年もいた」とも報じているのだが、ここで注目すべきは、「現実逃避」「若年女性」「定価より安く販売」といった記述が、従来の薬物依存者がまとっていた自堕落な犯罪者といったイメージや、あるいは「末端価格にして......」といった報道に代表される薬物取引の拝金主義的なイメージとは異なる雰囲気を醸し出しているということだ。
深刻でありながらも、どこか深刻さに欠けて子どもじみた市販薬のオーバードーズ。そんな一般的な印象を映像化した作品のひとつに、フジテレビドラマ『新宿野戦病院』(2024、ネットフリックスにて配信中)があるのだが、脚本を担当する宮藤官九郎の絶妙な肌感覚は、現代日本における「オーバードーズ」の位置付けを、日系アメリカ人の軍医であるヨウコの視点を借りて次のように表現している。
ヨウコ (英語で)この小娘が!? オーバードーズ!?
日本人の病院スタッフ (患者の友人に)何時ごろ何の薬を何錠のんだか分かる?
ヨウコ (英語で)急いで胃洗浄しないと! 〔中略〕
MDMAか? それとも......
日本人の医師 (日本語で)ああ、市販の鎮痛剤だ
これ1000錠のんでも死なないやつ(※1)
TBSドラマ『不適切にもほどがある!』(2024、ネットフリックスにて配信中)では、昭和的価値観を背負った中年男性を令和のコンプライアンス社会にタイムスリップさせた宮藤。彼は、同年夏に放映された本作『新宿野戦病院』にて、医療格差の激しいアメリカの現実を生き抜いてきた日系アメリカ人女性を令和の新宿に放り込んでみせたのだが、上の引用に言及される「MDMA」と「市販薬」は、危険なアメリカ社会と、平和な日本社会を、それぞれに象徴していると言えるだろう。
かくして、劇中の「聖まごころ病院」に勤務する看護師も言うように、本作におけるアメリカの位置付けは、その社会保障のあり方を日本と比較してみれば「みんなちょっとずつイヤな気持ち」になってしまうような国とされるのだが(※2)、 そうしたアメリカからやってきた軍医・ヨウコは、ポスト・コロナの日本がとりもどすべき「まごころ」の象徴のようにも描かれる。
ただし、本作がその「まごころ」を届けようとしているのは、あくまでもアメリカナイズされることのない「小娘」としての患者たちであることを忘れてはならない。劇中で繰り返されるMDMAと市販薬の対比が象徴するように、日本の若者のあいだで流行している市販薬の「オーバードーズ」の脅威は、往々にして矮小化されがちであり、そうした傾向を助長しがちなクリエイターの態度は、やはり「不適切」と言わざるをえないだろう。
たとえば、市販のせき止めシロップには「コデイン」という成分が含まれている場合があるのだが、そうした市販薬の乱用について、日本とアメリカのどちらが深刻かを競い合うことは、現状においてあまり意味がない。
体内でモルヒネに変質するコデインは、日本においては2014年以降、これを含む市販薬の販売個数が制限され、かつまた購入の際の年齢確認などが課せられてきた。しかし、『オーバードーズ くるしい日々を生きのびて』(2025)の著者・川野由起も指摘するように、「22年の調査によれば、市販薬を主に使う薬物とする症例の薬の内訳(複数選択)のうち、「コデイン含有群」が男性76・5%、女性71・6%となり男女ともに最も高かった」という。(※3)
このように、日本のコデイン対策は決してうまくいっているとは言えないのだが、一方のアメリカでは、「コデイン」は「処方薬となって」おり、たとえインターネットであっても「コデインを含むせき止めなどは購入ができない」とされる。(※4) 要するに、この問題について日本はアメリカの後塵を拝しているのだが......。
さて、こうした報告を聞いて、あなたはいったい何を思うだろうか。先に私は、危険なアメリカに安全な日本を対峙させるビジョンを「不適切」だと評価した。けれども、こうした「コデイン」の流通と規制の違いが、即「今では日本よりアメリカの方がクリーンかつ安全なのだ」といった結論につながると主張されたならば、あなたはきっと首を傾げるはずだ。
事実、コデインをめぐる日本の対応は、それがアメリカの方針を参照しているにもかかわらず、ときにあまりに不可解だ。
そもそも、ソーダで割ったコデイン入りの咳止めシロップは、アメリカにおいて「リーン」や「パープル・ドランク」と呼ばれ、学生から芸能人にいたるまで、多くの人々によってドラッグ代わりに使用されている。その蔓延ぶりは多くの死者を出すほど深刻であり、だからこそFDA(アメリカ食品医薬局)は、2017年の段階で、病院で処方される鎮痛剤「コデイン」を含んだ咳止めシロップなどの使用を厳格化し、使用を18歳以上に引き上げるという決定をした。だが、その知らせを受けた日本の厚生労働省は、日本国内では「12-18歳において、中毒関連症例に関する副作用報告がないこと」と、さらに、アメリカはアメリカの自己都合で規制しているといったことを理由に挙げて、2018年、コデイン制限引き上げをアメリカ並みにするといった決断を見送ってしまっているのだ。 (※5)
つまり、たとえどんなに現実の乱用ぶりがひどくとも、報告がなければクリーンとされ、政策も進められない。報告が多ければ多いで、規制は強まり、不法な取引が横行する。いずれにせよ、こと「オーバードーズ」の問題においては、「善も悪もアメリカが先を行き、その後を日本が追っている」といった構図は、すでに時代遅れとなっているのである。
片時も手放せないペインキラー
麻薬や危険ドラッグの代わりに、合法的に入手可能な市販薬を過剰に摂取してしまう。あるいは、単純に咳止めや痛み止めを目的として市販薬に手を出した人が、そのまま依存してしまう。彼らは大概、「犯罪者」である前に「被害者」であるのだが、そうした依存者に対する正しい理解は、日本でもアメリカでもなかなか浸透することがない。
確かに、1980年代に始まった「ジャスト・セイ・ノー」(アメリカ)や「ダメ。ゼッタイ。」(日本)といった公的なキャンペーンは、麻薬や覚醒剤をわかりやすい「悪」としてイメージづけることに成功した。けれどもその裏で、市販薬や処方薬に含まれる麻薬物質が法的にグレーな状態で流通していたことについて、私たちは今、認識を新たにしなければならない段階にきている。
すでに述べたとおり、アメリカにおいてコデイン入りの咳止めシロップのソーダ割りは、「リーン」や「パープル・ドランク」という通称でドラッグ化しているのだが、それでもやはり、その摂取については医療行為とも乱用ともつかないグレーなものとされがちだ。
一例として、テキサス州に暮らすパレスチナ難民の日常を描いたネットフリックスのダークコメディ『Mo/モー』(2022-)のワンシーンを観てみよう。
何をしても上手くいかない主人公のモーは、第1話からスーパーでの銃乱射事件に巻き込まれてしまう。病院への搬送を拒否し、ヤブ医者のチェンに傷口を縫ってもらうモー。だが、麻酔なしの治療はとても耐えられるものではなく、そんなモーにチェンは、コデイン入りの咳止めシロップをまぜた怪しい飲み物を渡すのだった。
チェン ほら、これでも飲みなよ。
モー リーンはごめんだ。ヒューストンのレジェンドもたくさん犠牲になった。〔ラッパーの〕ピンプ・Cだろ、ビッグ・モーだろ、それから、DJスクリューも......。
チェン 別にハイになれって言ってんじゃない。痛み止めだよ。
モー それより、なんか歯を食いしばれるものをくれよ。......ああぁ、もうダメだ!(コップのなかのリーンを飲み干す)
チェン おいおい、ゆっくり飲めよ。ゆっくり。
モー (落ち着きを取り戻す)
チェン 何本か持って帰りな。痛みが引くまで飲めばいい。ソーダとキャンディで割るんだ。(※6)
モーが最初、かたくなにリーンを拒絶するのは、薬物教育のおかげというよりむしろ、彼がリスペクトするヒップホップ・アーティストたちの死が教訓となっているからだ。
だが、そんなモーも痛みに負けてリーンを飲み干す。その後、痛みのためというよりも、ただ日々のつらさを忘れるために「リーン」にハマっていく彼の様子は、決して「かわいいもの」ではない。車の運転席で、観覧車の座席で、そして床屋での立ち話の最中にさえ、モーはリーンが手放せない。
友人 恋人のマリアは、おまえがこの店でバー・ベイビー〔=リーン中毒者〕みたいにそれを飲んでることを知ってるのか?
モー これはペインキラー〔=鎮痛剤〕だ。なにか、オレはクラリチン〔アレルギー鼻炎薬〕を飲むときにも、そのたびに彼女に言わなきゃいけないのか?
結局、リーンが原因で、モーは恋人のマリアに別れを切り出されてしまう。思えば、少年時代にアメリカに亡命するも、20年以上亡命申請が先延ばしにされてきた彼は、ときに違法なコピー商品を販売し、ときに麻薬の運び屋を強制されたりもするのだが、それでもみずからが薬物に手を出すことはせずに生きてきたはずだった。にもかかわらず、「ペインキラー」はスルリと彼の日常に入り込み、そして彼の人生を壊していく。
かくして、ペインキラーを発端とする薬物被害は、いまや世界中で社会問題となっているのだが、それはコデインのような成分を一つずつ規制していくだけでは到底くいとめられるものではない。国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部長を務める松本俊彦は、上述した川野の著書『オーバードーズ』のなかで、鎮静剤の代替わりの目まぐるしさについて以下のように警鐘をならしている。
オーバードーズでよく使われているせき止め薬に含まれている成分「コデイン」などは、14年に「濫用等のおそれのある医薬品」として販売規制の対象になりました。一方で、同年にはインターネットでの市販薬販売ができるよう規制緩和も始まりました。すると今度は、別の総合感冒薬がオーバードーズの主流の医薬品として使われ始めます。「アセトアミノフェン」という成分が入っていて、肝機能障害に直結しこれも危険です。21年の8月に「デキストロメトルファン」を含んだせき止め薬が市販薬として販売されるようになり、特定の製品がオーバードーズに頻用され始めました。製薬会社の利益にもつながるため、販売規制の動きは進みづらいところがあります。(※7)
ペインキラーのオーバードーズ。その闇を深めているのは、一度試すと引き際が判断できないという、薬物そのものが持つ恐ろしさにとどまらない。松本が指摘するように、覚醒剤の原料やモルヒネに類似した成分を含む薬が合法的に販売され続けているという社会の仕組みそのものが闇に他ならないのである。
───────────────────
本稿に引用されているネットフリックスからの引用は、配信されている日本語・英語字幕を参考にして、引用者が翻訳したものである。
(※1)ドラマ『新宿野戦病院』エピソード2、ネットフリックス、2024.
(※2)『新宿野戦病院』エピソード1.
(※3)川野由起『オーバードーズ くるしい日々を生きのびて』朝日新書、2025、Kindle.
(※4)川野、Kindle.
(※5)https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000197891.pdf
(※6)ドラマ『Mo /モー』ファーストシーズン、エピソード1、ネットフリックス、2022.
(※7)川野、Kindle.